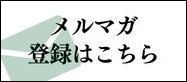今年度の稲盛研究助成対象者とのこれまでの対象者が交わる「盛和スカラーズソサエティ(3S)交流会」。今年も自然科学、人文・社会科学を問わずさまざまな分野から研究発表があり、ポスターの前では専門を超えた自由闊達な議論が交わされました。交流会を終えたばかりの発表者と今年度の助成対象者の方に、感想を聞いてみました。
ポスター発表者

稲葉 靖子さん (宮崎大学 農学部 准教授)
発表タイトル:植物が発熱する仕組みの解明とその利活用に向けた基盤研究
いつもと違う視点からの質問に刺激を受けました
私は、花で熱を出して送粉者を誘引したり、低温障害を回避する植物の研究をしています。これまでに発熱に関連する遺伝子を数多く見つけられたので、今後は真の発熱誘導遺伝子を見つけたいと思っています。発熱植物はソテツなど大きなものが多いので、まずは実験に適した小さくて栽培しやすいモデル発熱植物を見つけたいと思います。ポスター発表では他分野の先生方から「一つの花への温度刺激が同じ株の他の花にも伝わるのか」や「温度センシングや長期的・短期的な発熱誘導の機構は分かっているのか」といった質問を受けました。植物の大きさなど難しいところもあるのですが、これから是非検証していきたいと思います。

小野 大輔さん(名古屋大学 環境医学研究所 講師)
発表タイトル:すべての種に共通して存在するであろう“祖先型概日時計”の同定
自身の研究を発信するよい機会になりました
今日の発表では普段の学会以上に多くの方に興味を持っていただきました。自分の研究をより多くの方に知っていただき、共同研究などへつなげていきたいという思いを持っているので、今回は時間が限られていましたが、もう少し時間をかけて多くの先生方とお話しできればよかったなと感じました。他の方の発表では、「植物が発熱する仕組みの解明とその利活用に向けた基盤研究」というテーマに興味を持ちました。植物が熱を発するということを考えたことがなかったので、例えば動物との共通原因があれば面白いなと思いました。普段なかなか異分野の先生と出会う機会はありませんが、「こんな研究をしている先生がいるんだ」ということを知ることが横断研究につながっていくと思うので、今日のような機会はとても重要だと感じています。

井出 和希さん(大阪大学 感染症総合教育研究拠点 特任准教授)
発表タイトル:学術誌の「質」を考える:リスクベーストアプローチによる言語化の試み
研究文化の多様性を実感できました
私のポスターでは、学術誌の優劣は単純に二分できるものではなく、グラデーションが存在すること、そしてその優劣を定める具体的な要素を言語化する試みについて発表しました。来場者の方々との対話を通じて強く感じたのは、学術論文や出版のあり方が分野ごとに大きく異なっているということです。ある分野では査読が必須ではなかったり、別の分野では出版社によるカテゴリー分けが実態と乖離していたりと、それぞれの分野が置かれた文脈や慣習の違いが浮かび上がりました。
また、学術研究全体に視野を広げると、実用性に対する評価の仕方など、研究内容に対する価値観もコミュニティごとに多様であることを実感しました。今回の経験を通じて、私は研究者それぞれが拠り所とする分野の文化には揺らぎや多様性があることを改めて認識し、異なる価値観を持つ研究者同士が対話を重ねることの重要性を感じました。

山口 新平さん(東邦大学 理学部 准教授)
発表タイトル:父ゲノムをもたない脳をもつマウスの作製
分野を超えた対話が新鮮でした
分野外の人から素朴な疑問をたくさんいただいて、自分の説明不足を感じるとともに、そんなところに疑問を持つんだなというのが新鮮でした。父ゲノムと母ゲノムの働きが違うということや、発生工学的な手法が可能ということに驚かれている方がいました。片方のゲノムだけのマウスが死んでしまうメカニズムに興味を持たれる方がいて、そこは今後詰めていかなければならないなと感じました。また、「学術誌の『質』を考える:リスクベーストアプローチによる言語化の試み」という発表を聞き、学術誌の評価には二元論的な良し悪しだけではなく、グラデーションがあり、雑誌ではなく論文で評価しなければならない、エディターによって違うといった話がとても参考になりました。文系の先生もいらっしゃるような会は普段参加する機会がないので楽しかったです。
今年度助成対象者
3Sの営みに感銘を覚えました
私は、自身の研究課題のみならず、各団体の助成事業の掲げる理念や哲学にも関心を抱いています。実際、この度の助成に申請した動機の一つには、3S(盛和スカラーズソサエティ)の営みがあります。3S交流会は他に類を見ないものであり、当該年度の助成対象者に加え、これまでの助成対象者や関係の先生方が一堂に集まる貴重な機会となります。本会に参加してみて、多世代にわたる、多様な専門性を有する研究者との出会い、つまり、縦と横の両方向に広がる豊かな人的ネットワークの構築が図れるように実感しました。ある意味では、助成金をはるかに超える価値があるように思います。また準備に多大な労力や時間を要する本会が、継続的に開催されてきたことに感銘を受けました。井村先生や中西先生、審良先生等と直接お話しでき、また新たに多くの研究者の方々や稲盛財団の皆様にお会いできたことを大変ありがたく思います。
ロボット開発を通じて脱力の秘密に迫りたい
ヒトなどの生き物は脱力状態を巧みに使って多様な動作を行いますが、そのような動作の一つが打楽器演奏です。私自身も演奏するのですが、ドラムを上手くたたくには脱力が必要です。人工筋肉をアクチュエーターに使うと、ロボットの腕に、生物のような脱力した状態を作り出すことができます。この人工筋肉を使った打楽器演奏ロボットの開発を通じて、私は二つの目的を達成したいと思っています。一つはロボットが強化学習の中でいかにして脱力を活用した動きを獲得していくのかを知ること、もう一つは出力の小さなロボットのポテンシャルを引き出し、大きな仕事をさせる方法を探求することです。
このように私の研究はロボット工学や生物学などを横断する、学際的な側面が大きいのですが、ポスター発表では人文系を含む異分野の方とのコミュニケーションを学ぶとても良い機会になりました。全く異なる分野のポスター発表では「高校生にも分かるように易しく」とお願いしました(笑)。
誰も作ったことのないカーボン材料に挑戦したい
マッカイ結晶という、まだ誰も作ったことのない3次元ナノカーボン材料の制作を試みています。3次元の繰り返し構造を作るのは非常に難しいのですが、私たちが新しく見つけた化学反応や分子を使って、第一歩としてまずは一つの周期構造を持つ分子を作ることに挑戦します。マッカイ結晶は穴や空間を持つ3次元構造や半導体特性を生かしたさまざまな特性が予測されており、3次元構造のアレンジでさらに多くの特性が期待されます。
交流会では本当に色々な分野の方々が集まっていることに驚きました。私と同じ化学者は少なかったですが、ポスター発表では異分野の方が相手だからこその大胆な思いつきを含めたディスカッションができたのがとても良い刺激になりました。
参照していた論文の著者の方と初めてお話しできました
ポスター発表の中では、分野が近いので「軌道磁化に基づく非対角応答の学理開拓」という発表が一番興味深かったです。以前から発表者の打田先生の論文を参照させていただいていて、今日はじめて実際にお話しすることができました。もっぱら物理の話をしていたのですが、分野や研究手法が同じなので、強いインスピレーションを受けました。ポスター発表者は同じ物理でも物質を研究されている方もいれば宇宙を研究されている方もいて、非常に興味深かったです。他分野の方とお話しをしていると最初はかみ合わないこともあるのですが、話していく中で根本的な考え方に気づくことがあります。今後の研究の展望としては、強相関化合物CaRuO₃において観測された桁外れなサイズ効果を、実際のデバイスへ応用していくことを目指しています。
「稲盛財団Magazine」は、稲盛財団の最新情報を配信するメールマガジンです。メールアドレスのみで登録可能で、いつでもご自身で配信解除できます。