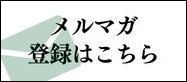2025年10月16日、17日の二日間、稲盛財団(京都市下京区)において、「稲盛科学研究機構(InaRIS)フェローシップ」のアドバイザリー・ボード・ミーティング(以下、ABM)が開催されました。ABMではInaRISフェローが自身の研究の進捗と展望について発表し、運営委員や他分野のフェローとの活発な議論が行われました。
InaRISは、短期的に成果を求めるのではなく、好奇心の赴くまま存分に、壮大なビジョンと大きな可能性を秘めた研究に取り組んでもらうため、2019年に設立されたプログラムです。毎年1,000万円、10年間にわたり総額1億円を助成しています。
ABMに先立ち、2023年度(情報)フェローの亀井靖高氏(九州大学教授)と田中由浩氏(名古屋工業大学教授)、および2020年度(量子)フェローの高柳匡氏(京都大学教授)と野口篤史氏(東京大学准教授)に対する中間審査が行われました。審査終了後、中西重忠機構長によりABMの開会が宣言されました。
今年のABMは、初参加となる2025年度(数学)フェローの戸田幸伸氏(東京大学教授)と平岡裕章氏(京都大学教授)の発表からスタートしました。

続いて、2021年度(生命)フェローの西増弘志氏(東京⼤学教授)と山口良文氏(北海道⼤学教授)、2022年度(材料)フェローである深見俊輔氏(東北⼤学教授)と藤田大士氏(京都⼤学准教授)、2024年度(医学・医療)フェローである鈴木洋氏(名古屋⼤学教授)と星野歩子氏(東京大学教授)が、研究の進捗状況を報告しました。

InaRISは設立から6年目を迎え、フェローの専門分野も多彩になっています。各フェローの発表後には、分野の垣根を超えて活発な質疑応答が行われました。16日夜には、京都市内のホテルに場所を移して懇親会が開かれ、参加者たちはなごやかに交流を深めました。

中西機構長による総括では、6年目を迎えたInaRISの歩みを振り返るとともに、研究のさらなる発展への期待が語られました。分野を越えた対話を通じて新たな視点や協働の芽が育まれた今年のABMも、盛況のうちに幕を閉じました。今後もフェローたちがそれぞれの探究を深化させ、未来を切り拓く研究を推進していくことが期待されます。
「稲盛財団Magazine」は、稲盛財団の最新情報を配信するメールマガジンです。メールアドレスのみで登録可能で、いつでもご自身で配信解除できます。