この度は、2023年度稲盛研究助成に採択していただきまして、誠にありがとうございます。国際的・国内的に、難民政策が転換期にある中、私は、本研究を通して、現代における難民保護の在り方を検討し、学術的に貢献したいと考えています。どうかよろしくお願いいたします。
2022年2月24日のロシアによるウクライナ軍事侵攻以降、G7加盟国は、ウクライナ避難民の受け入れを進めた。このとき、日本は、他国のように「一時的保護」の枠組みで一時的に対応するのではなく、新たに「補完的保護対象者の認定制度」を設置し、羈束的に在留資格を認めるかたちで、ウクライナ避難民を受け入れようとした。本研究は、この動きに着目した。
本研究では、日本のウクライナ避難民の受け入れと「補完的保護対象者の認定制度」の導入について、国会、出入国管理政策懇談会、難民認定制度に関する専門部会などの会議録をもとに検討することを試みた。その結果、日本における「補完的保護対象者の認定制度」の導入は、迫害を受けるおそれのある地域への送還を禁止する「ノン・ルフルマン原則」の適用範囲の拡大と「人道配慮による在留許可」の発展という、国内の難民保護の歴史の延長線上に位置付けられることを明らかにした。また、ウクライナ避難民の受け入れは、日本が補完的保護に関する国際人権規範を受容することを助長したと言える。
土田千愛(2024)「2023年入管法改正における補完的保護対象者の認定制度に関する一考察」『移民政策研究』(16):20–34
土田千愛(2024)『日本の難民保護―出入国管理政策の戦後史』慶應義塾大学出版会
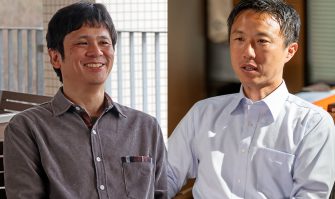
2025年度InaRISフェロー紹介動画を公開しました!

自然科学系と人文・社会科学系の研究者を支援する「稲盛研究助成」の助成金贈呈式と、これまでの助成対象者の交流を目的とした「盛和スカラーズソサエティ(3S)」の交流会が19日、ザ・プリンス京都宝ヶ池(京都市左京区)で開かれました。

3月7日、稲盛財団は 2025年度稲盛研究助成の対象者50名を発表しました。405件(自然科学系319件、人文・社会科学系86件)の応募から厳正な審査を経て選ばれた、自然科学系40件、人文・社会科学系10件に、1件当たり100万円を助成します。研究に真に必要な経費であれば使途に制限はありません。

稲盛研究助成のこれまでの対象者が参加する「盛和スカラーズソサエティ(3S)交流会」。今年も昨年に続いてポスター発表で活発な議論が交わされました。交流会を終えたばかりの発表者と今年度の助成対象者の方に、感想を聞いてみました。

3月8日、稲盛財団は2024年度稲盛研究助成の対象者50名を発表しました。408件の応募から厳正な審査を経て選ばれた、自然科学系40件、人文・社会科学系10件に、1件当たり100万円を助成します。

稲盛財団は、5月23日、2023年度の稲盛科学研究機構(InaRIS: Inamori Research Institute for Science)フェローシップの申請受付を開始しました。

3月10日、稲盛財団は2023年度稲盛研究助成の対象者50名を発表しました。394件の応募から厳正な審査を経て選ばれた、自然科学系40件、人文・社会科学系10件に、1件当たり100万円を助成します。

私たちの食生活になじみの深いワカメやコンブなどは褐藻と呼ばれる海藻の仲間です。今回は、その褐藻の生殖や発生について研究をしている北海道大学の長里千香子氏の研究所にお邪魔し、詳しいお話を伺いました。

「稲盛科学研究機構(InaRIS)フェローシップ」の運営委員やフェロー同士が研究内容について議論を交わす「アドバイザリー・ボード・ミーティング」が10月4日、稲盛財団(京都市下京区)にて開催されました。 I...
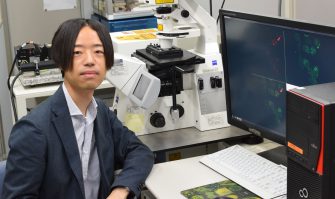
大阪公立大学の弓場英司氏は、高分子化学や有機合成化学の手法を使ってDDSのための、微小な「脂質ナノカプセル」を開発しています。いったいどのようなカプセルなのでしょうか。詳しいお話を伺いました。

3月11日、稲盛財団は2022年度稲盛研究助成の対象者50名を発表しました。411件の応募から厳正な審査を経て選ばれた、自然科学系40件、人文・社会科学系10件に、1件当たり100万円を助成します。

私たちの日々を彩ってくれる音楽を、学術的に研究していくことでどのようなことがわかるのでしょうか。文学や社会学、統計学など、他の分野の手法を取り入れながら音楽の裾野を広げる研究を行う九州大学の西田紘子准教授に、音楽学研究の魅力をお聞きしました。

7月1日、2022年度の稲盛研究助成の申請受付を開始しました。

稲盛財団は、2021年5月21日、2022年度の稲盛科学研究機構(InaRIS)フェローシップの申請受付を開始しました。今年度の募集対象分野は「物質・材料」研究の前線開拓です。
人文・社会系領域
